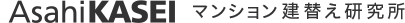これまでも、全員合意でマンションを解体して売却を行う事例はないわけではありませんでした。たとえば、東日本大震災の被災マンションの中で、建替えを選択せずに、被災した建物を解体したうえで売却することを全員合意で決議した事例もあるようです。
ただし、敷地一括売却については、特別法があるわけではなかったので、仮にマンションを解体して売却を計画するような場合には、民法の共有物の変更(民法251条)により全員合意が必要とされていたことから、ハードルが高くその実現が困難であったわけです。その意味で、区分所有者、議決権および敷地の共有持ち分割合の各5分の4という高いハードルではありますが、特別多数決議で敷地一括売却を決議することができるようになった意義は大きいと思います。
次に、この法律による敷地一括売却制度のもう一つの意義は、決議後に、敷地売却組合を設立し、最終的に「分配金取得計画」の決議と都道府県知事等の認可を経て、権利消滅期日に要除却認定マンションの権利がマンション敷地売却組合に移転することです。すなわち、権利消滅期日にはマンションの土地・建物の所有権はマンション敷地売却組合に帰属するため、この時点で敷地売却組合と買受人とが契約をすることで、権利は買受人に移転します。この点は敷地一括売却を円滑に行うために非常に重要なポイントとなるわけです。
仮に区分所有者間において敷地売却についての合意ができた場合でも、その後の手続きについて特段の規定がない限りは、買受人は区分所有者全員と売買契約をしなければいけません。この場合、敷地売却に同意した区分所有者についても、「売却には同意したけれども、売却相手は違う人(あるいは会社)が良い」ということもできるわけであり、その結果として一人でも買受人に対する売却に同意しない区分所有者がいる場合には、敷地売却は完了しません。
その意味では、新しい法律は、敷地売却の決議とともに、敷地売却の実現についても視野に入れたものとなっているわけであり、この点については高く評価できるのではないかと考えています。
(20161118一部訂正)